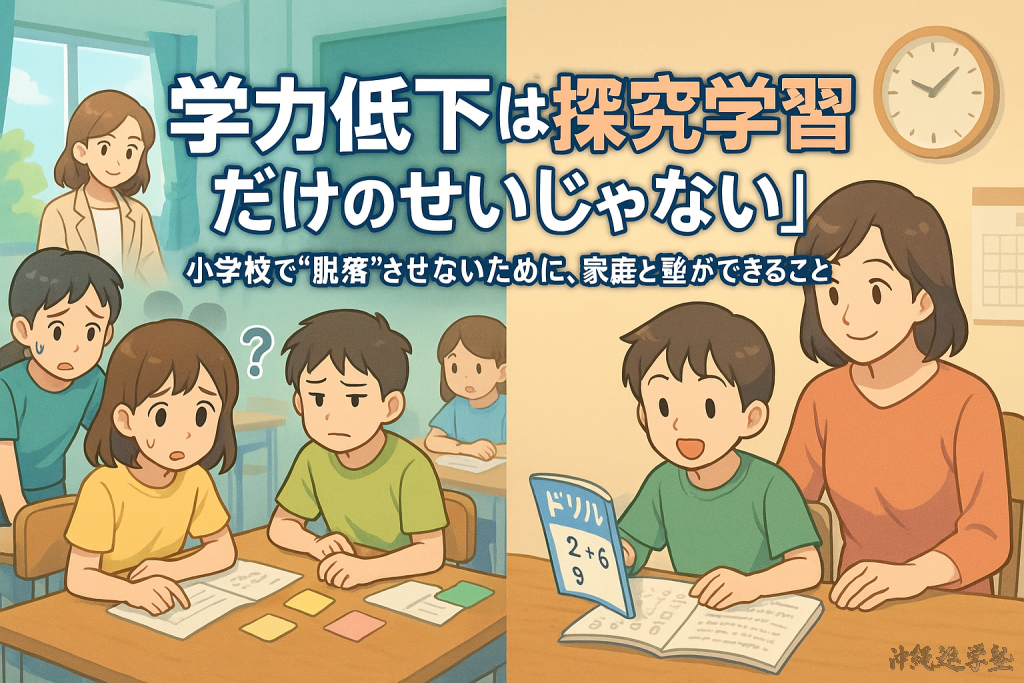
動画ダイジェスト
文部科学省が実施した2024年度の「経年変化分析調査」で、小学6年生と中学3年生の学力が、前回2021年度より大きく低下していることが明らかになりました。特に小学校の国語・算数、中学校の国語・数学・英語で、全国的にスコアの低下が見られています。
さらに、家庭の社会経済的背景(SES:Socio-Economic Status)が低い層ほどスコアが低く、同じSESの層を比べたときも、小学校・中学校の国語や数学で、SESが低い子どもの方がスコアの落ち込みが大きいことも報告されています。
つまり、
- 学力は本当に下がっている
- 特に経済的に厳しい家庭の子どもほど、落ち込みが大きい
という二つの事実が、データとして出てきているわけです。
1.参考記事の要約:「探究・グループワーク」が基礎学力の時間を奪っている?
今回の議論のきっかけとなったのが、東洋経済education×ICTに掲載された以下の記事です。
参考記事:
「学力低下」の原因はスマホでもコロナ禍でもない?法学者も指摘「小学校での探究やグループワークの増加」が問題か
記事の主なポイントを、中学生と保護者の方にも読みやすい形でまとめると、次の通りです。
(1)塾・現場の感覚:「入ってくる中1の学力が明らかに落ちている」
- 分数の足し算以前に、四則計算(+−×÷)があやしい中1が増えている。
- 語彙力も不足しており、「小学生の内容のやり直し」から始める塾も多い。
- そのため、「小学生のうちから塾で基礎を固めるコース」を強化する動きが出ている。
(2)探究学習・グループワークが「読み書き計算の時間」を圧迫
- 2020年度の学習指導要領改訂で、小学校に「探究学習」「グループワーク」が本格的に導入。
- その結果、教師が基礎を教える時間や、ドリルや宿題で反復させる時間が減っている、という指摘がある。
記事では、具体例として「時間の計算」が挙げられています。
ある保護者のケースでは、「13時36分の30分後は何時何分?」という基礎的な時間の計算問題が解けず、子どもが泣き出したそうです。親が5分教えたら理解できたにもかかわらず、小学校の授業では「時間ってなんだろう? みんなで考えてみよう」といった探究型の活動だけで、時間の計算の仕方そのものは教えていなかったといいます。
算数が得意な子でさえ、きちんと教えれば5分でわかる内容です。それを「教えていない」こと自体が問題だ、というのが記事の主張です。
(3)グループワークは「応用編」──基礎がない子には逆効果
- 現場の小学校教員への取材では、「グループワークや探究は、本来“応用編”。基礎ができている子には効果的だが、基礎が不安な子には逆効果」という声が紹介されている。
- 法学者・木村草太氏も、「探究やグループワークは効率がよくない。その時間で計算ドリルや語彙を覚える反復学習が減ってしまっている」と指摘している。
(4)カリキュラム増&時間不足で「わからない所に戻れない」教室
- 別の現場教員は、「カリキュラムの量が増えたので、授業をスピーディーに進めないといけない。わかっていなさそうでも、立ち止まって丁寧に教え直す時間がない」と語っている。
- 結果として、「時間の計算」「時計の読み方」など、本来時間をかけて習得すべき基礎が、十分に定着しないまま次の単元へ進んでしまう。
(5)宿題の有無と地域差──「中学受験エリアは宿題ほぼゼロ」も
- 長野市のように、夏休みにワーク100ページ出すような地域もある。
- 一方で、東京・世田谷など中学受験率が高い地域では、「小学校の宿題はほぼ出ない」ケースが増えている。
- 背景には、「中学受験の勉強の妨げになるから宿題を出してほしくない」という保護者のニーズもある。
- しかし、塾に通っていない子にとっては、その宿題が唯一の反復練習の場であり、宿題がなくなると、四則計算もおぼつかないまま中学へ進んでしまう。
(6)塾に通えない家庭ほど「読み書き計算」が危うい
- 少子化と大学全入時代で、高校・大学の門戸は広がっているが、「読み書き計算」が不十分なまま社会に出る若者が増えかねない。
- 公文などで基礎を補うにも、算数+国語だけで月1万5千円前後かかり、物価高・実質賃金の低下もあり、その費用を払えない家庭も多い。
参考記事全体としては、
「スマホやコロナ禍“だけ”のせいにするのではなく、小学校での探究・グループワーク偏重で『読み書き計算』の時間が削られていること、そして、そのしわ寄せが塾に通えない子どもに集中しているのではないか」
という問題提起になっています。
2.探究学習が「悪者」なのではなく、順番の問題
ここからは、那覇市で進学塾を運営し、中学受験・高校受験について情報発信をしている私の個人的な見解です。
(1)入学前から始まっている「スタートラインの差」
現場でいちばん強く感じるのは、小学校入学時点でのスタートラインの差です。
- 小学校入学前に、ひらがな・カタカナが一通り読めて、簡単な文章なら理解できる子
- ひらがなから、まさに「学校で初めて教わる」子
この二つのグループで、1〜2年生のうちに読解力(文章を読み取る力)に大きな差がつきます。
読めない子は、授業のスピードについていくのが大変です。先生の説明を聞く前に、「板書を写す」「教科書の指示を読む」段階でつまずきます。その状態のまま3年生に上がり、「分数・小数・文章題」が本格化することで、一気に差が目に見える形で表面化します。
(2)「脱落組」は、家庭と第三者の関わりが薄い層に集中している
私の感覚としては、次のようなケースで、いわゆる「脱落組」が増えていると感じます。
- 家庭が基本的に学校任せで、家庭学習のフォローがほとんどない
- 塾・公文・通信教育など、第三者の目が入らない
- 保護者自身も忙しく、「テストの結果を見て、具体的にどうサポートするか」まで考える余裕がない
これはあくまで私個人の現場感覚ですが、「学校だけでカバーしきれない部分を、家庭も第三者もフォローしていない子」ほど、早い段階で勉強からこぼれ落ちやすいという傾向は、かなりはっきり見えています。
3.勉強がすべてではない。でも「何も得意がない」はしんどい
ここで大事なのは、
「勉強がすべてではない」=「だから勉強はどうでもいい」
という話ではない、ということです。
私自身の個人的な意見としては、
- 勉強でトップを目指さなくてもいい
- けれど、何か一つ、「自分はこれをやり切った」と言える経験は、人生を支える土台になる
と考えています。
スポーツでも、音楽でも、美術でも、プログラミングでも構いません。ただ、現実問題として、
- 勉強で躓き続けている
- かつ、部活や趣味でも「これだけは頑張っている」というものがない
という子は、小・中・高校と進む中で自己肯定感を保つのがとても難しいのです。
多くの「やり切る子」は、幼少期からの小さな成功体験の積み重ねで育っていきます。だからこそ、小学校の学習で大きく躓かせないためのフォロー体制は、本当に重要だと感じています。
4.先生たちを責めるのは筋違いだと思う理由
この記事を読むと、「やっぱり学校がダメなんだ」「昔の先生の方がよかった」という声が出てきがちです。しかし、私の感覚では、今の先生たちはむしろ昔よりも丁寧で、子ども一人ひとりに向き合おうとしているように見えます。
問題は、
- 学力格差が大きいクラスを、一人の担任が同時に見る構造
- 学習指導要領の内容が増え、求められる「学力」の幅が広がっていること
- さらに、SNSリテラシー、AIとの付き合い方、多様性理解など、新しいテーマも学校に求められていること
です。
昔よりも「先生に求める仕事」が増えているのに、時間も人手も増えていません。その中で、「探究もやりなさい」「ICTも使いなさい」「一人ひとりに寄り添いなさい」「働き方改革で残業は減らしなさい」と言われているのが、今の学校現場です。
ですから、「先生がもっとやるべきだ」と責めるのは、おそらく筋違いです。むしろ、
- 学校に“何でもかんでも”期待しすぎない
- 家庭と地域、塾などの第三者が役割を分担する
という発想への転換が必要だと、私は考えています。
5.スマホ・ゲームの影響も含めた「複合要因」として考える
文科省の資料を見ると、スマホやゲームの時間と学力の関係も、はっきりと示されています。
- スマホ・ゲームの利用時間はここ数年で増加している。
- 勉強時間はわずかに減少している。
- 家庭の経済状況が厳しい子どもほど、勉強時間が短く、スマホ・ゲームの時間が長い傾向がある。
つまり、本当の姿は、
- 探究・グループワークの時間増加
- スマホ・ゲームの利用増加
- 家庭の社会経済的な格差
- 入学前からの「読み書き」の習得差
などが複合的に絡み合っていると見るべきでしょう。
「学力低下の原因はこれだ!」と単純化してしまうと、本当の課題を見誤りかねません。探究学習やグループワークそのものには、考える力・対話する力を伸ばすメリットもあります。
大事なのは、
- 「基礎」→「応用」の順番が崩れていないか
- 基礎を誰が、どこで、どのようにフォローするのか
という設計の問題です。
6.保護者ができる「小学校で脱落させない」3つのポイント
ここからは、中学生とその保護者向けに、「じゃあ結局どうすればいいの?」に答えるパートです。
(1)「読み・書き・計算」だけは最低限チェックする
難しいことを全部やろうとしなくて大丈夫です。ただし、次の3つだけは、小学生のうちに何とかしておきたい基礎だと考えてください。
- スラスラ読めるか(音読・黙読)
- 簡単な文章を書けるか(短文でよい)
- 四則計算・時間・小数・分数の基本ができるか
もしここが怪しいと感じたら、
- 市販のドリルを「1日1ページ」から始める
- できたら必ず小さく褒める(スピードよりも「続いたこと」を評価)
という形で、「小さな達成体験」を積ませてあげてほしいと思います。
(2)「脱落サイン」を見逃さない
例えば、こんなサインが出ていたら、要注意です。
- 宿題に異常に時間がかかる(30分で終わるはずが毎日2時間)
- 国語の文章題や算数の文章題になると、問題文すら読みたがらない
- 「算数きらい」「国語きらい」という言葉が増えた
- テストの見直しを一緒にやろうとすると、極端に不機嫌になる
これらは、「もうできないから触れられたくない」というサインであることが多いです。その時に、
- 「なんでこんなのもできないの!」ではなく、
- 「どこからやり直したらわかるようになるかな? 一緒に探そう」
というスタンスを取れるかどうかが、子どもの自己肯定感に大きく影響します。
(3)塾や第三者を「敵」ではなく「チームメイト」にする
スポーツの世界では、専門コーチの指導を受けている子が結果を出しやすい、というのは多くの方が体感としてお持ちだと思います。勉強も同じです。
- 学校の先生は「受験のプロ」ではなく、生活習慣・学習習慣を整える専門家
- 受験や個別の弱点補強は、塾や家庭教師など、別の専門家の方が得意
と考えた方が、役割分担として自然です。
もちろん、塾は無料ではありません。だからこそ、
- 「全部塾任せ」か「まったく塾なし」かの二択ではなく、
- 家庭の状況に合わせて、必要なタイミングで必要な部分だけ頼る
という発想が大事になります。
7.沖縄の入試は確実に難しくなっている
これは、沖縄の高校入試・中学入試の問題を長年見てきた私の実感ですが、沖縄県の入試問題も、確実に難しくなっています。
- 単純な知識問題から、文章を読み解き、自分の考えを書く「記述式」の比重が増えている。
- 中堅校でも、全国レベルの思考力・表現力を問う問題が少しずつ取り入れられている。
その一方で、
- 小学校で「読み書き計算」でつまずく子
- 中学校で基礎を取りこぼしたまま、入試学年を迎える子
は、確実に増えています。
このギャップが広がると、
- 一部の上位層だけがどんどん伸びる
- 真ん中〜下位層は、「何をどう勉強したらいいか分からない」まま時間だけが過ぎていく
という構図になりかねません。
だからこそ、沖縄の中学受験・高校受験について情報発信をしている立場として、「小学校での基礎の取りこぼし」を、家庭と地域でどう防ぐかを、これからも発信していきたいと考えています。
8.まとめ:「探究かドリルか」の二者択一から抜け出そう
最後に、この記事全体のポイントを整理します。
- 全国のデータを見ても、小6・中3の学力はこの数年で下がっている。
- 特に、家庭の社会経済的背景が厳しい子どもほど、スコアの落ち込みが大きい。
- 東洋経済の記事が指摘するように、小学校での探究学習・グループワークの時間増加が、「読み書き計算」の時間を圧迫している可能性は高い。
- しかし、原因はそれだけではなく、スマホ・ゲームの利用増加、宿題の減少、入学前からの学力差、家庭のサポート力の差など、複数の要因が絡み合っている。
- 現場の先生たちはむしろ丁寧に頑張っており、「学校に全部任せる」時代はもう終わっている、と考えた方がいい。
- 保護者にできるのは、「読み・書き・計算」の最低限のチェック、「脱落サイン」を見逃さず責めずに一緒にやり直すこと、塾や第三者を「チームメイト」として部分的に活用すること。
探究学習も、グループワークも、本来は子どもたちの未来にとって大切な学びです。問題なのは、それらを「基礎の上に積み上げる」設計になっているかどうかです。
まずは読み書き計算で“土台”をつくり、その上に探究やグループワークを乗せていく。
この順番を守ることができれば、「探究=学力低下の犯人」という単純な図式から抜け出せるはずです。
沖縄の子どもたちが、勉強でも、部活でも、将来の仕事でも、「自分はこれをやり切った」と胸を張れる経験を一つでも多く持てるように。そのための情報発信と、現場での支援を、これからも続けていきたいと思います。
執筆者情報
比嘉 大(ひが たけし)
沖縄県を拠点に、中学受験・高校受験に関する情報発信を行う教育インフルエンサー。講師歴20年以上。学習塾の運営のほか、調剤薬局、ウェブ制作会社、ウェブ新聞「泡盛新聞」の経営など、25歳で起業して以来、自社7社・間接経営補助10社を展開。「教育が沖縄を活性化させる」という志を持ち、地域学力や家庭教育の課題について積極的に発言している。








この記事へのコメントはありません。