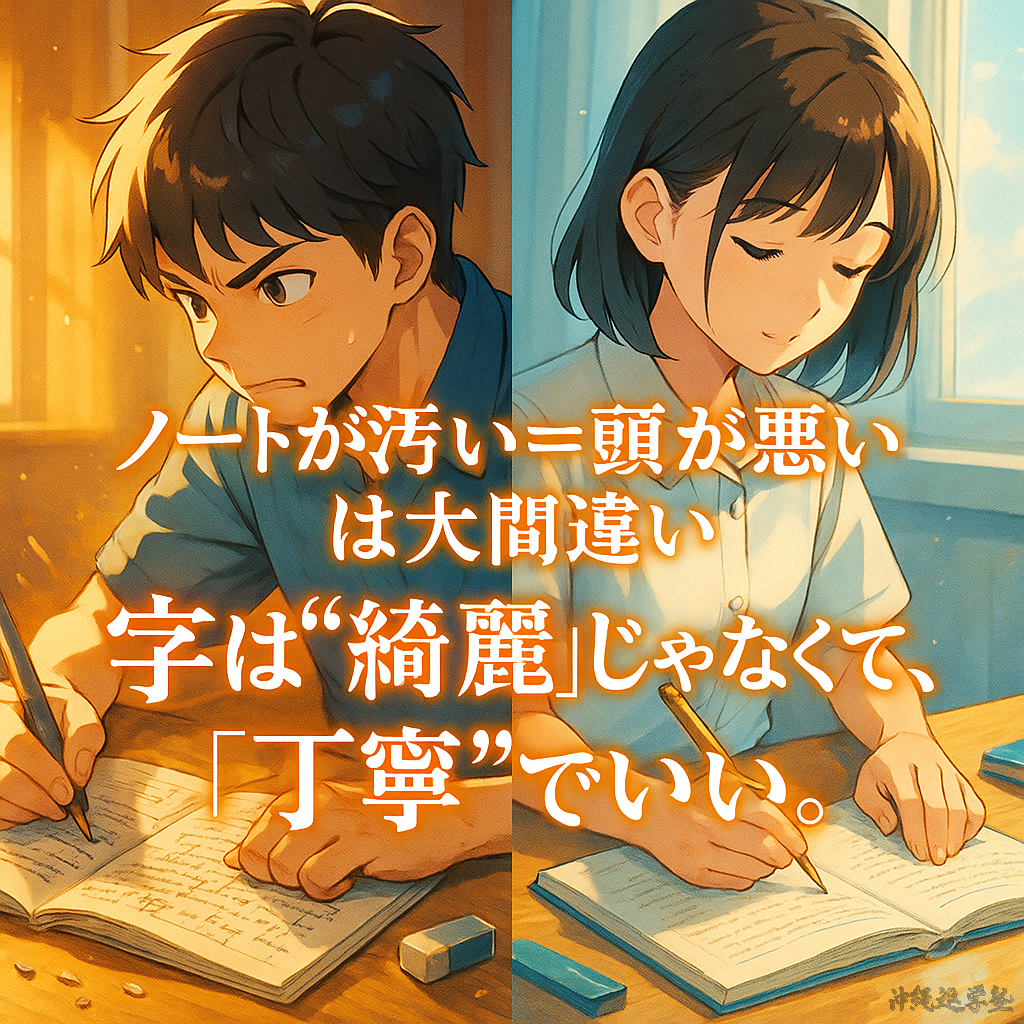
参考記事
出典:『「ノートが汚い=頭が悪い」は大間違い…東大専門塾の元講師が明かした「成績が伸びる子」の意外な特徴』(PRESIDENT Online, 2024年)
東大受験専門塾「鉄緑会」の元講師が、長年の指導経験から「ノートが汚い=賢くない」という固定観念を否定した記事です。
著者によれば、ノートが乱雑な生徒ほど思考のスピードが速く、頭の中で次々に考えが浮かんでいるケースが多いとのこと。
つまり「ノートが汚いのは能力の低さではなく、思考が手に追いつかない伸びしろの証拠」だといいます。
また、東大理科Ⅲ類の合格者の中には、裏紙に殴り書きをして勉強していた学生もいたとの実例も紹介。
彼らも、最初から美しいノートを書いていたわけではなく、受験勉強の過程で「伝わる書き方」を身につけていったというのです。
筆者は最後に、「ノートが汚い=才能がない」と決めつけず、子どもが“振り返りたい”と思ったタイミングでノート術を教えるべきだとまとめています。
「このノート、本当に大丈夫ですか?」
「先生、この子のノート、ひどいんです。これで本当に勉強についていけるんでしょうか?」
保護者面談で、そんな声を耳にすることがあります。
ページを開くと、文字が走り書きで線も乱れ、途中式が抜け落ちている。
心配になるお気持ちは痛いほどわかります。
けれど私は、20年近く教育の現場に立ち、確信しています。
ノートの汚さと学力は、まったく関係ありません。
むしろ、ノートが汚い生徒ほど、頭の回転が速く、考えの展開スピードが早い傾向があります。
“書く手”より“考える脳”が先に動いているのです。
それは「だらしなさ」ではなく、「才能のあふれ出た証」。
沖縄進学塾でも、そんな“ノートの荒れた秀才たち”に何度も出会ってきました。
乱雑なノートの中に、光る思考があった
ある中学1年の男の子がいました。
計算式は途中で切れ、ページの余白にはメモのような走り書き。
見た瞬間、保護者の方は不安そうに「この子、ついていけてますか?」と尋ねました。
でも私は、ノートをじっと見つめて確信しました。
そこには、他の生徒にはない“スピード感”がありました。
「ここはこうしたら早く解けるんじゃないか」
「この式は別の形でも書けるぞ」
──そんな思考の火花が、文字の乱れとなって紙に刻まれていたのです。
ただ、本人は「ミスが減らない」と悩んでいました。
だから私は、こう提案しました。
> 「今日は時間を気にしなくていい。とにかく“読みやすく”書いてみよう」
すると、彼はゆっくりと手を動かし始め、普段の2倍の時間をかけて答案を完成。
全問正解。文字も整い、本人が一番驚いていました。
その日を境に、彼は「読める字を書くこと」を意識するようになり、ノートが見違えるほど整いました。
やがて塾内テストでは上位1割に入り、最終的に難関高校へ合格。
“書く”ことが、思考を整理する力に変わった瞬間でした。
字を丁寧に書く理由──「採点者への配慮」がすべて
私が生徒に伝えるのは、ただひとつ。
> 「きれいな字を書け」ではなく、「採点者が読める字を書け」。
テストは「自分のため」ではなく、「他人に伝えるため」の表現です。
どれだけ頭の中で正解を導けても、読めない字で書けば不正解です。
だから私は「美しい字」よりも「伝わる字」を重視します。
一画一画を整えるというより、「相手を思いやる字」を意識してもらうのです。
実際、「きれいに書く」と意識するよりも、「採点者に伝わるように書く」と伝えるだけで、
生徒の字は驚くほど変わります。
目的を意識すると、人は自然と丁寧になるのです。
思考の速さと字の汚さは、矛盾しない
「ノートが汚い=集中していない」というのは、よくある誤解です。
実際には、思考のスピードが手を超えているだけ。
東大理Ⅲの合格者にも、裏紙に殴り書きをしていた学生がいたという話は象徴的です。
思考が爆発している瞬間ほど、人は“形”を気にしていられないのです。
けれど、試験本番は違います。
答案を書くという行為は、「他人に理解されるように自分を表現すること」。
つまり、ノートの乱雑さは“原石の状態”。
それを“磨いて伝える力”に変えるのが、受験勉強の本質です。
私がよく生徒に言う言葉があります。
> 「走るときは走っていい。でも、ゴールの前では整えよう。」
デジタル時代における「書く力」
今の中高生は、紙よりもスマホやタブレットに慣れています。
レポートもオンライン提出、LINEで連絡──手書きの機会は減る一方です。
だからこそ、私はこう伝えます。
> 「名前だけは、丁寧に書け。」
理由は単純です。
人生で「自分の字」を残すのは、履歴書、契約書、そして願書の署名のとき。
その瞬間に、自分の字が“覚悟の形”になります。
AIが文章を作り、デジタルが主流になる時代でも、
手で書く字には“心”が宿ります。
書くとは、自分の存在を残すことなのです。
ノートは「心の鏡」である
ノートが汚いからといって、焦らないでください。
それは、思考が動いている証拠かもしれません。
もちろん、「読める字」を意識することは必要です。
しかし、それは「罰」ではなく、「表現の技術」として身につければいいのです。
子どもが自分のノートを見返して、
「自分でも読めない」「もう少しきれいにしたい」と感じたとき。
その瞬間が、書く力を教える最高のタイミングです。
保護者の方には、こう伝えたいと思います。
> ノートは“成績の結果表”ではなく、“思考の成長記録”です。
> 汚いノートの中にも、未来のひらめきが必ずあります。
どうか、その「汚さ」の中に、光を見つけてあげてください。
比嘉 大(ひが たけし)
教育インフルエンサー/沖縄県拠点|中学・高校受験情報の発信者
沖縄県を拠点に、中学受験・高校受験に関する情報発信を行う教育インフルエンサー。
学習塾の運営のほか、調剤薬局、ウェブ制作会社、ウェブ新聞「泡盛新聞」の経営など、
25歳で起業して以来、自社7社・間接経営補助10社を展開。
「教育が沖縄を活性化させる」という志を持ち、
地域学力や家庭教育の課題について積極的に発言している。








この記事へのコメントはありません。