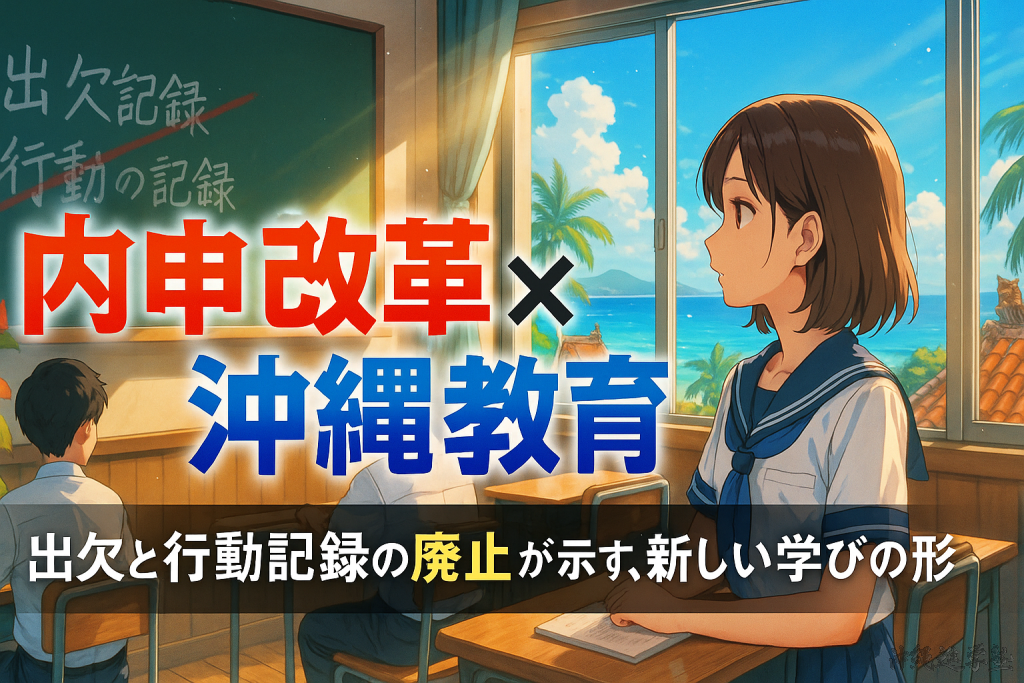
参考記事の要約
愛知県教育委員会は、不登校の増加や学びの多様化を背景に、2027年度の公立高校入試から内申書に記載していた出欠記録と行動の記録(授業態度・生活習慣などの10項目)を廃止します。保健室登校・別室登校・教育支援センター・オンライン学習など、教室外で学ぶ生徒が増える中、出席日数を評価基準にするのは現在の状況に合わないと判断したためです。加えて、性別欄の記入も廃止されます。出欠記録の廃止は、東海地方では岐阜県に続く動きです。
参考記事:不登校の増加等受け…公立高校入試で使う内申書から出欠や行動の記録を廃止へ 性別の記入欄も(Yahoo!ニュース)
1. 制度が変わる教室の風景(起)
「先生、内申点って、もう関係ないんですか?」――授業後に中学2年生がそう尋ねてきました。声の色には、安堵と不安が同居していました。これまでの高校入試では、学力だけでなく、授業態度、提出物、そして出席日数までが評価の対象でした。ところが2027年度から愛知県では、内申書から出欠記録と行動の記録が外れ、評価は教科の成績中心へと舵を切ります。
背景には、不登校や別室登校、オンライン学習など学びの多様化があります。教室にいなくても学びを続けられる選択肢が広がる中、単純な出席日数で評価することは、事情の異なる生徒間で公平性(評価基準が誰にとっても納得できるかという観点)を損ねかねません。今回の見直しは、そうした現実への応答だと言えます。
2. 愛知と沖縄に共通する現実(承)
このニュースを聞いて、私はすぐに沖縄の現状を思い出しました。沖縄でも不登校の増加や通学の難しさ(離島・遠距離・家庭事情など)があり、教育支援センターやオンライン学習の活用が広がっています。つまり、愛知と同じく「出席日数だけで生徒の努力や学びを測るのは現実的ではない」という課題を共有しています。
一方で、毎日通い、提出物を期日どおりに出し、地道に取り組む生徒の日々の努力は、数字から外れると見えにくくなります。沖縄の学校現場でも、部活動や地域行事、ボランティアなど、テストの点数では測れない頑張りが数多くあります。こうした「数字に出ない成長」をどう評価に残すか――これは愛知と沖縄の共通課題です。
塾で多くの生徒を見てきた経験上、内申は学力と完全一致はしないものの、学び方の姿勢(指示を受け止める力、反復練習の継続、締切の遵守など)を映す鏡として機能してきました。特に内申が高い生徒は、基礎を固める訓練で伸びやすい傾向があります。逆に内申が低い生徒は、実力が高い場合と低い場合の差が大きく、後者は立て直しに時間がかかることが多い。これは沖縄でも同じです。
評価の公平性という観点では、先生も人間である以上、完全な客観性は難しく、相性や印象が影響することはゼロにはできません。特に小規模校・離島校では教員と生徒の距離が近く、評価が関係性に左右されやすい現実もあります。それでも大多数の先生は、日々の観察と記録に基づいて誠実に評価しています。だからこそ重要なのが、評価基準の見える化(何をどのように評価するのかの公開)です。基準を透明にすることで、生徒・保護者の納得感が高まり、先生自身も守られます。
| 項目 | これまで | 2027年度以降(愛知) | 沖縄への示唆 |
|---|---|---|---|
| 出欠記録 | 欠席日数が内申に反映 | 廃止 | 出席日数重視の見直し(事情の異なる生徒への配慮) |
| 行動の記録 | 授業態度・生活習慣を10項目で評価 | 廃止 | 主観評価のばらつき低減/基準の透明化が鍵 |
| 性別欄 | 男・女を記載 | 廃止 | 多様性尊重の流れは全国共通の課題 |
| 評価の軸 | 学力+出欠+生活態度 | 学力中心 | 学力以外の可視化(記録の残し方)の工夫 |
3. 新しい評価時代への備え(転・結)
制度が変わっても、子どもたちの成長に必要なものは変わりません。これからの入試では教科成績の比重が高まる一方で、数字に出ない努力をどう伝えるかがより重要になります。沖縄の保護者・生徒に向けて、次の3点を提案します。
- 家庭で「数字に出ない成長」を言語化する:協調性、責任感、挑戦する姿勢、地域活動などを、日付・内容・関わった人・得られた学びの形でメモ(例:「2025/07/15 地域清掃30分、班リーダー体験、声かけの難しさと工夫を学んだ」)。
- 学習は「理解→反復→可視化」の循環で:理解した内容をノート1ページに要約→小テストで反復→間違いの原因と対策を1行で可視化。反復の記録が、姿勢と伸びやすさを示す根拠になります。
- 学校・塾・家庭の「基準合わせ」:提出物の締切・提出形式・評価配点など、明文化された基準を家庭にも共有。曖昧さを減らすことで、努力の方向性が一致し、無駄が減ります。
社会に出れば、上司や顧客など他者の評価を避けて通ることはできません。義務教育における内申という仕組みは、その予行演習でもありました。今回の改革は、その「予行演習」をより透明で納得できる形に進化させるチャンスです。数字だけが評価のすべてではない時代に、沖縄の子どもたちが自分の価値を堂々と示せるよう、私たち大人も評価の基準づくりに関わり、言葉で支え続けたいと思います。
※用語の注釈:公平性=誰にとっても納得できるルールや運用であること/透明性=評価の基準や手続きが見える形で説明されていること/可視化=努力や成長を第三者に伝わる形で残すこと。
“`








この記事へのコメントはありません。